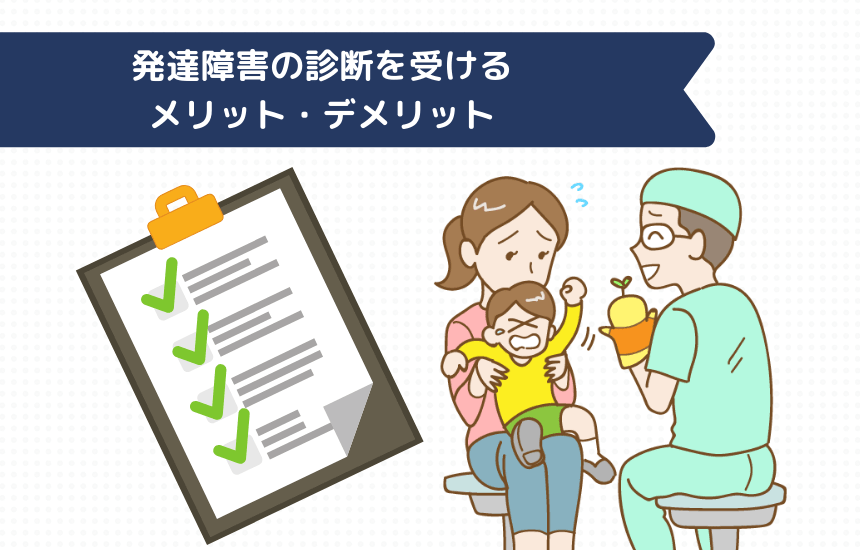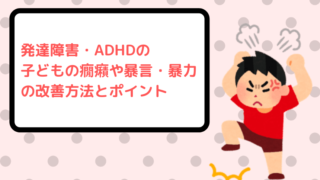「発達障害の診断ってどこで受けるの?」
「発達障害ってどうやって診断するの?」
「発達障害の診断を受けるメリット・デメリットって?」
今、お子さんに発達障害の診断を受けさせようか、迷っていらっしゃると思います。
すごくこわいですし、不安ですよね…。
もし、
「あなたのお子さんは発達障害です」
と宣告されたら、それだけで、これからの育児や子育てが不安になりますよね…。
だからこそ、診断を受けたほうがいいと思っても、なかなかあと一歩が踏み出せない…というお母さんもいらっしゃると思います。
発達障害の診断を受けることは親子にとってメリットもありますし、デメリットもあります。
また、診断を受ける前に知っておくべきこと、理解しておくべきこともあります。
そこで、今回は発達障害の診断がどんなものか知りたい方、受けるべきか迷っている方に向けて、発達障害の診断基準やメリット・デメリットについて解説していきたいと思います。
【診断を受ける、その前に…】
発達障害について知っておくべき3つのこと
発達障害が注目されるようになった今、
「発達障害は生まれつきだから治らない!」
「発達障害の原因は遺伝だから仕方ない」
など、発達障害に関して、お母さんやお父さんを不安にさせるような情報や広告が乱立していますよね…。
このような根拠のない言葉で、たくさんのお母さんが不安を感じ、子育てや育児に苦労しています。
また、このような情報が、発達障害の診断を受けるか迷わせるひとつ要因になっているとも考えられます。
でも、安心してください。
発達障害は生まれつきだから治らないということはありえません。
これらを踏まえて、発達障害の診断をお子さんに受けさせる前に知っておいていただきたいことがあります。
それは、以下の3つです。
◯発達障害は”脳の発達の遅れ”
◯発達障害と健常児の明確な区別はない
◯発達障害の原因は”遺伝”と”環境”の相互作用
では、それぞれの点について、もう少し詳しく見ていきましょう。
発達障害は”脳の発達の遅れ”
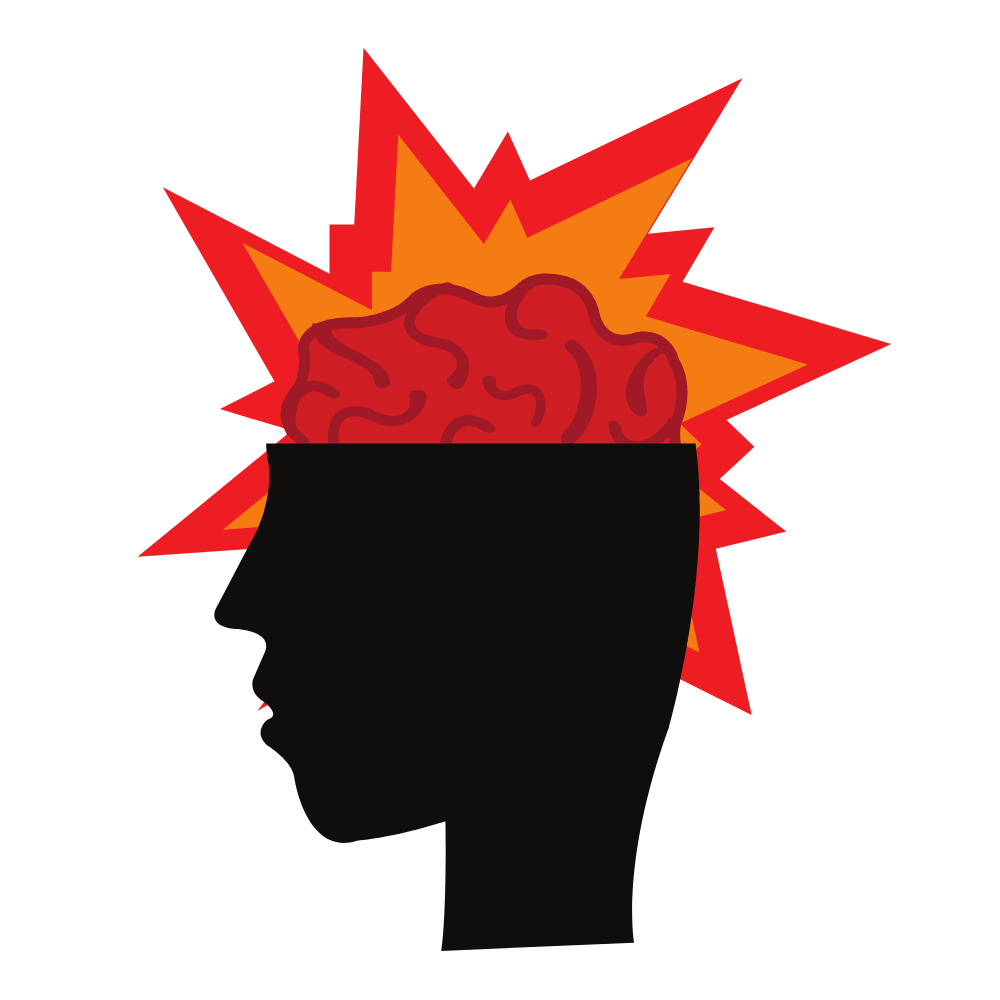 「発達障害は遺伝が原因だ!」
「発達障害は遺伝が原因だ!」
「発達障害は生まれつきだから仕方ない。」
このように、発達障害の根本的な原因に関して、誤った情報がありふれていますよね。
まず、発達障害の根本的な原因は「脳」にあります。
つまり、
発達障害=脳の発達の遅れ(脳の機能障害)
ということです。
脳は、人間の生活のすべての指令を司る部分です。
「見る」「聞く」などの基本的な”機能”はもちろんのこと、「記憶」「感情」「話す(コミュニケーション)」などの”機能”もすべて脳が重要な役割を果たしています。
また、自分の感情や欲望をコントロールしたり、目標を立てて計画を立てたりするのも脳の重要な”機能”の一つです。
ただ、何らかの原因で異常がもたらされ、通常より脳の発達が遅れると、これらの”機能”に障害が生まれることがあります。
これが「発達障害」です。
でも、脳は一生をもって変化しつづける特殊な器官です。
(もちろん、脳が変化しやすい時期とそうでない時期がありますが、0~8歳の子どもは特に脳が変化しやすい時期とされています。)
そのため、何らかの原因で脳の発達が遅れ、機能障害が生じたとしても、適切なトレーニングによって、未熟な脳を発達させることで、発達障害は改善することができます。
ですので、
「発達障害は生まれつきだから治らない!」
というのはウソです。
もちろん、脳が変化しやすい時期はありますが、その時期にしっかりと発達の遅れている領野をトレーニングすることで、発達障害の特性や症状を改善することはできます。
また、脳は環境や日々の経験によって、どんどん変化していきます。
(特に0~8歳はみるみる変化していきます。ですので、「幼児教育」が大切になります。)
つまり、“脳科学”の分野からすると、そもそも「発達障害=生まれつき」という表現がまちがっているし、「生まれつきだから改善しない」ということもありえないのです。
発達障害と健常児の明確な区別はない
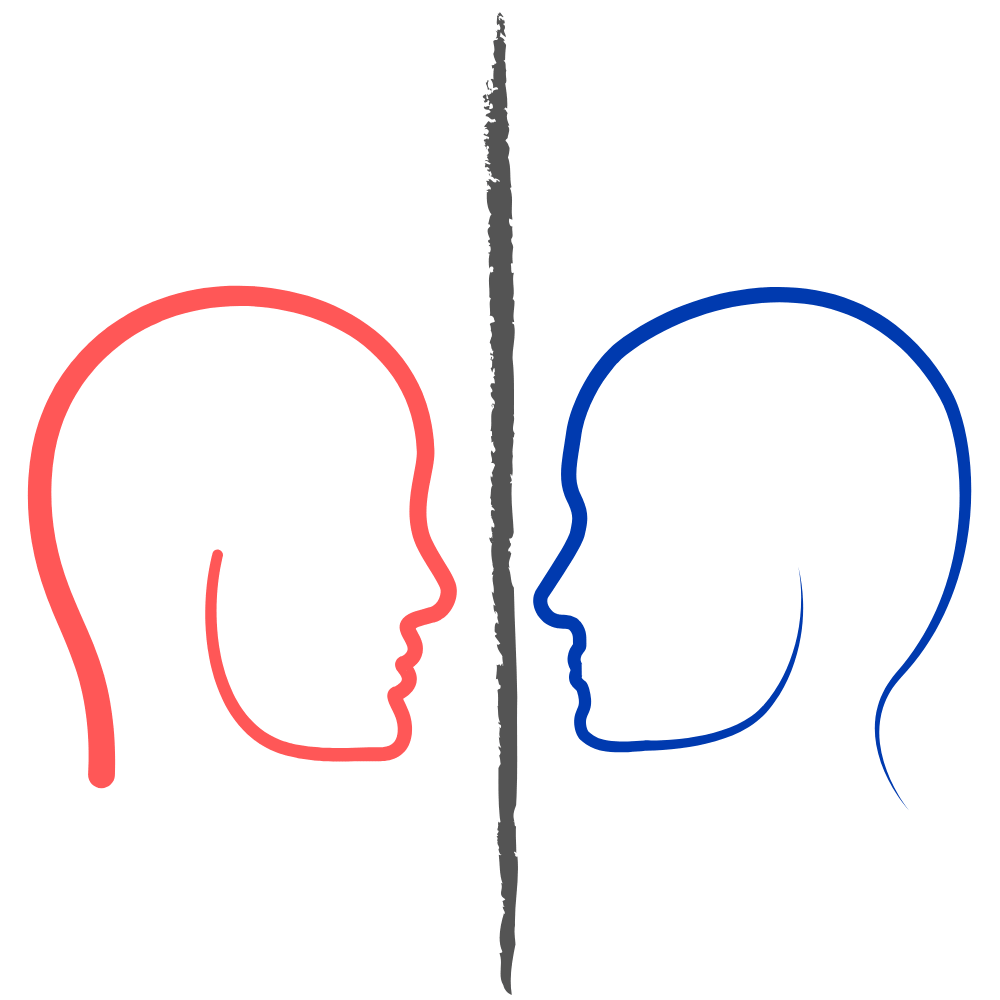 2つ目は、「発達障害と健常児の間に明確な区別はない」ということです。
2つ目は、「発達障害と健常児の間に明確な区別はない」ということです。
発達障害の診断の際に用いられる基準にはアメリカ精神医学会が定めた「DSM(※)」や、世界保健機関(WHO)が定めた「ICD-10」があります。
ただ、これらの基準は発達障害のお子さんに見られやすい特徴や症状をまとめたものであって、基準としては非常にあいまいなものです。
そして、その診断基準のなかには、健常児と言われるお子さんが当てはまる項目も存在しています。
また、発達障害児と健常児はそもそも線を引いて、右と左に分けられるほど単純なものではありません。
発達障害のお子さんでも、健常児のお子さんと変わらない特徴をもっていて、言動の一部のみ発達障害の特性をもっていることがあります。
逆に、健常児のお子さんでも、部分的に発達障害の特性をもっているケースもあります。
ですので、明確に区別することはできないのです。
そのため、発達障害児と健常児は、本来明確に区別できるものではないことをしっかりと理解しておくことが必要です。
発達障害の原因は”遺伝”と”環境”の相互作用
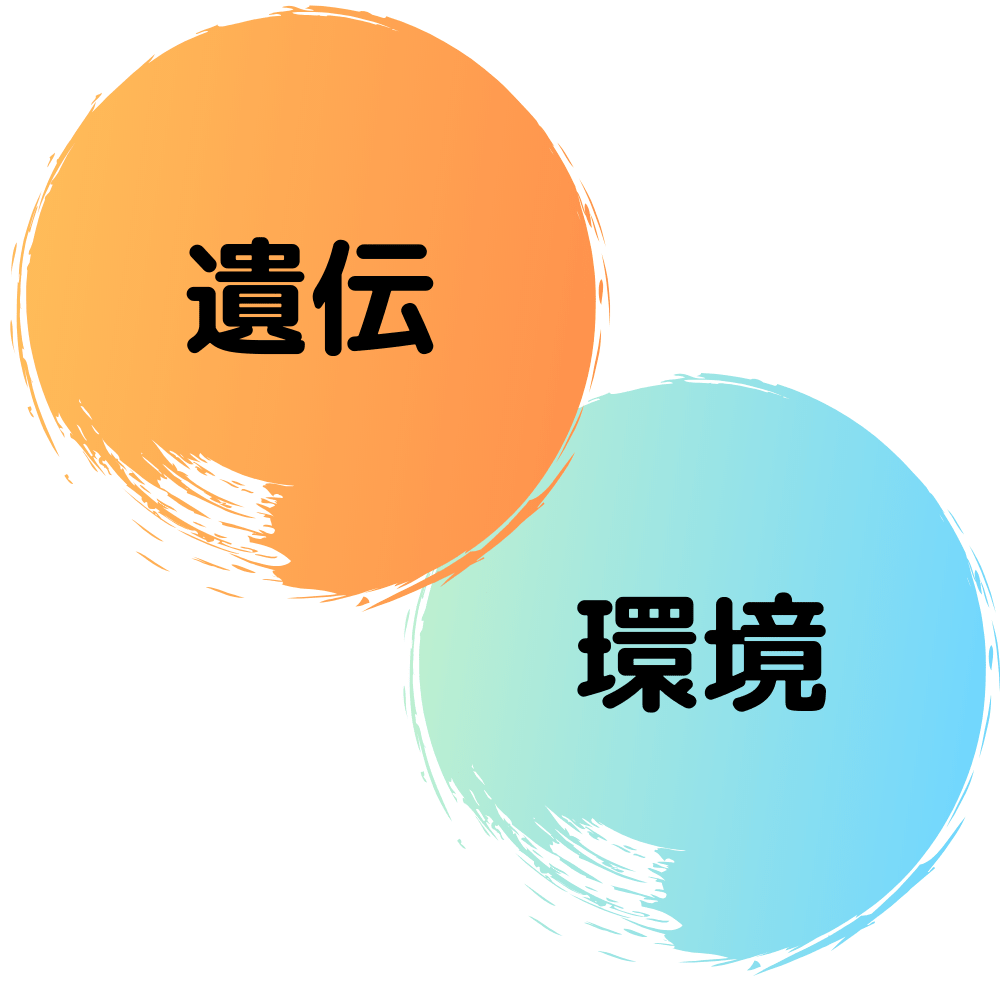 3つ目は発達障害の要因に関してです。
3つ目は発達障害の要因に関してです。
発達障害の原因は、時代によってさまざまな議論が展開されてきました。
最初のころは「冷凍マザー仮説」と言われて、お母さんの育て方が原因だと批判された時代がありました。
(一生懸命子育てをしているお母さんからすると、怒りを覚えますよね…。)
もちろん、発達障害に”遺伝は関係しています。”
たとえば、両親のいずれがADHDに関連する遺伝子をもっていた場合、お子さんへの遺伝率は約80%、LD(学習障害)の遺伝子を持っていた場合、遺伝率は約50%と言われています。
ただ、現在に至るまでのさまざまな研究によって、発達障害は”環境”も大きく影響することがわかってきました。
ただ、環境といっても、これが意味する幅は広いです。
一般的な育児環境から妊娠中の母体内の環境、農薬などの化学物質、食べ物などによる栄養の偏りなど、その要因はさまざまです。
つまり、遺伝的な要因がなくても、環境的なリスクで発達障害的な症状がつくられ、発達障害と診断を受けることがあるのです。
ですので、発達障害は決して”生まれつき”だけではなく、生まれてからのさまざまな環境的要因によって”作り出される可能性もある”のです。
【迷ったら診断を受けるべき?】
診断を受けるメリット・メリット
発達障害の診断を受けることには、メリット・デメリットがあります。
先にデメリットから見ていきましょう。
最大のデメリットは、
「”発達障害”という診断を受けることで、お母さんにショックと不安を与え、今後の子育てにずっと影響を与える可能性がある」
ということです。
“障害”という言葉は想像以上にお母さんやお父さんに重くのしかかってしまいます。
また、そのような診断を受けると、無意識のうちに子どもを見る目にバイアス(偏見)やフィルターがかかるようになります。
(時には虐待に走ってしまったり、ネグレクトにつながる場合もあります。)
そのため、発達障害の診断というのはお母さんやお父さんにってお、それくらい大きなものであるということです。
そして、これが最大のデメリットになります。
ただ、その一方で大きなメリットもあります。
それは、
「診断を受けることで、お子さんの強みと弱みを見つけ出し、早めに対応・改善することができる」
という点です。
先ほどもお伝えしたように、
発達障害=脳の発達の遅れ(脳の機能障害)
です。
そして、脳は一生をもって変化しつづける特殊な器官です。
また、0~8歳の子どもは特に脳が変化しやすいです。
そのため、早めに診断を受けることで、お子さんの脳のどこに発達の遅れがあるのかを見極めることができます。
そして、脳が柔らかくて変化しやすい時期に適切な脳のトレーニングをすることで、発達障害の症状を改善したり、進行をストップすることができます。
逆に、発達障害であることをなんとなく気づいていても、診断を受けずにそのまま放っておくと、引きこもりや不登校などの二次障害につながり、取り返しのつかないことになります。
(脳は歳をとればとるほど、硬くなり、変化しづらくなっていきます。)
これらのメリット・デメリットを踏まえると、個人的には早めに診断を受けることを推奨します。
【どこで・どうやって診断するの?】
発達障害の診断基準と診断方法
 基本的に発達障害の診断は基本的に小児科や児童精神科などで受けることができます。
基本的に発達障害の診断は基本的に小児科や児童精神科などで受けることができます。
また、その際には基本的に以下の2つの手法が取られます。
①親御さんへの質問
②診断基準を用いての観察
それぞれについて、もう少し詳しくみていきましょう。
①親御さんへの質問
お子さんが発達障害か診断する上で、診察室でお母さん・お父さんからお話を聞きます。
発育歴やふだんの家庭でのようす、保育園・幼稚園、学校でのようすなど、お子さんに関するさまざまなことを医師が質問し、それに答える形になります。
また、診断を受けるときに母子手帳や育児日記、保育園・幼稚園での連絡ノートなどがあると、手がかりにもなります。
ですので、診断を受ける際には持参することをおすすめします。
②診断基準を用いての観察
もう一つは、診断基準と照らし合わせながら、親御さんからのお話やお子さんのようすを観察する方法です。
このときに用いられる診断基準は、アメリカ精神医学会が定めた「DSM(※)」が中心ですが、世界保健機関(WHO)が定めた「ICD-10」が用いられることもあります。
DSMはアメリカ精神医学会から出版される「Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders(精神疾患の診断・統計マニュアル)」のことです。
DSMは2013年5月にこれまでのDSM4版(DSM-IV-TR)から、5版(DSM-5)に改訂されました。
【診断はあくまでも目安】
誤診の可能性の十分にある。
発達障害の診断は小児科の先生や精神科の先生によって診断されることが多いです。
ですが、そのような先生方のなかには脳科学の精通していない先生もいらっしゃいます。
また、診断方法についても、発達障害のお子さんに見られやすい特徴をまとめたリスト(DSM-5など)をもとに、医師が対象となるお子さんを観察したり、保護者の方から話を聞いたりして判断します。
そのため、いくら医師といえど、主観的な評価が入ることは否定できません。
つまり、発達障害と診断されても、誤診の可能性があるということです。
ですので、診断を受けても、それを必要以上に気にする必要はありません。
さいごに
ここまで発達障害の診断を受ける前に知っておいていただきたいことや診断の詳細やメリット・デメリットについて解説してきました。
診断を受けることはとても勇気が必要ですよね。
ですが、発達障害児の根本的な原因が脳であるなら、早く診断を受け、発達の遅れている脳の領野を発見するにこしたことはありません。
ですので、個人的には、診断を受けようか迷っているのであれば、早めに受診することを推奨します。
また、まだ踏ん切りがつかなかったり、イマイチ発達障害なのかわからないという方は、以下のページに発達障害のお子さんに見られやすい特性や症状をまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

![ナッツ[Nuts]](https://everyone-nuts.jp/wp-content/uploads/2019/08/nuts_logo01.png)